昨今、企業規模を問わず、会社と労働者との間の雇用や労働に関する争いやトラブル、労働基準法や労働契約法などのいわゆる労働法分野における労働トラブルといった労務問題(労働問題)が多発化・多様化・深刻化する傾向が見られます。
労務問題(労働問題)が深刻化すると、労使紛争(労働紛争)に発展し、経営に与えるコストやリスクが突然増大します。
労使紛争(労働紛争)には、次の2つの種類があります。
労働組合など労働者の労働関係上の利益を代表する労働者の団体と使用者(雇用主・事業主)との間で生じた労働条件や労使関係に関する紛争
集団的労使紛争の解決には、労働組合の団体交渉以外に、労働委員会(地方労働委員会、中央労働委員会)が紛争解決機関として重要な役割を担ってきました。
使用者(雇用主・事業主)と個々の労働者との間の個別的な関係での紛争・トラブルになります。
今までの日本の労使紛争といえば、集団的労使紛争が大きな地位を占めてきました。
高度経済成長時代の労使関係は、企業があげた利益を労使でいかに分配するかが団体交渉の中心にありました。
低成長期に入ると、企業が利益を上げにくい時代になり、労働時間の短縮や男女の雇用機会の均等化など、労働条件の改善の方に団体交渉の重点が置かれるようになり、労働者個人の権利意識の醸成も進みました。
また、労働者と企業を取り巻く環境の構造的かつ抜本的な変化、社会・経済・情報のグローバル化といった大きな枠組みの変化、バブル崩壊後の日本経済の構造的不況などにより、時代は停滞期から激変期に突入しました。
企業は生産設備の海外移転とリストラ(雇用調整)でコストダウンを図ると同時に、相次ぐ規制緩和もあり、正社員比率の低下・非正規社員の増員という形で人材流動化・人件費の変動費化を図りました。
その結果、国内の産業構造の空洞化が急激に進み、雇用・就業形態(就労形態)が多様化しました。
労使紛争(労働紛争)自体も多様化かつ個別化し、団体交渉を中心とする労使自治で集団的に経済的地位の向上を図る集団的労使紛争の仕組みに馴染まなくなりました。
労働組合の性質上、個別の対応を想定していないため、利害調整機能が働かず、組合員へのメリットを提供できなくなり、労働組合の組織率の低下という形で顕著に表れました。
集団的労使紛争という解決手段が機能しなくなったからといって、労務問題(労働問題)が減少するわけではありません。
むしろ、不況が長期化し、景気回復の見通しが立たない経済情勢のなか、企業も生き残りを賭け、労働条件の切り下げや配置転換、リストラや解雇といった手段を行使せざるを得ない状況に置かれました。
このこと自体、個別労使紛争(個別労働紛争)の火種をばら撒いているようなものです。
労務問題(労働問題)に直面している労働者は、経済成長期のように容易に転職という解決手段を使うことができず、いっそう失望感や閉塞感を強めており、単独で「企業を訴える」行動、つまり個別労使紛争(個別労働紛争)を選択するケースが増えてきました。
今後も個別労使紛争(個別労働紛争)の増加が予想されますが、個別的であるため、適切な解決策が見出せず、問題が長期化する傾向があります。
こうした動きに対応し、「円満な解決」「簡易・迅速な手続き」「費用負担が生じない解決システム」を実現すべく、厚生労働省は2001年10月に「個別労働紛争解決制度」を創設し、労使紛争(労働紛争)の迅速な解決を推進してきました。
また、2006年4月には簡易・迅速・専門的な司法手続きとして「労働審判法」が施行されました。
個別労使紛争(個別労働紛争)の最終的な解決手段として裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、職場の労使慣行等を踏まえることも重要となります。
このため、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、労務問題(労働問題)への専門性が高く、無料で個別労使紛争(個別労働紛争)の解決援助サービスを提供するセーフティ・ネットとして、次の制度が整備されました。
労働審判制度は、個別労使紛争(個別労働紛争)について、裁判官(労働審判官)と労働関係についての知識経験をもつ労働審判員からなる労働審判委員会が、地方裁判所において、3回以内の期日で審理を行い、調停による解決を試みつつ、調停が成立しない場合は、事件の内容に即した紛争解決案を定めた労働審判を下す手続きです。
調停制度や労働局等で「あっせん」などの手続きもありますが、相手方が出頭しないと手続きが進まないという問題があります。
労働審判では、相手方不出頭でも手続きを進めることができる点、迅速な紛争解決の実現を可能にしています。
制度的には「訴訟」と「調停」の中間的な役割と言えます。
厚生労働省の次の資料によると、個別労働紛争解決制度創設後、総合労働相談件数は年々増え続け、2011年度は110万9454件となり、2010年度から微減しているものの4年連続で100万件を超えました。
また、労働者と会社(雇用主・事業主)との間の労使紛争(労働紛争)件数を表わす「民事上の個別労働紛争」の相談件数は25万6343件で、それに対応した助言・指導件数、あっせん申請受理件数のいずれも過去最高を記録しました。
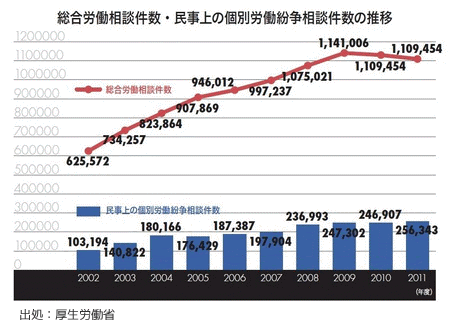
個別労使紛争(個別労働紛争)の内容に目を向けると、多様化の傾向が見られます。
個別労働紛争解決制度が発足した直後の2002年度と2011年度を比較すると、2002年度に最も多かった「解雇」に関する相談が、相対的にはまだ一番の割合を占めていますが、10ポイント近く(28.6%→18.9%)減少しました。
他方、「いじめ・嫌がらせ(パワハラ)」に関する相談が10ポイント弱(5.8%→15.1%)上昇し、「いじめ・嫌がらせ」「労働条件の引き下げ」「退職勧奨・出向・配置転換」が目立ってきました。
「自己都合退職」に関する相談が増えているのも特徴的です。「その他」の中には「セクハラ」や「パワハラ」も入ってきます。
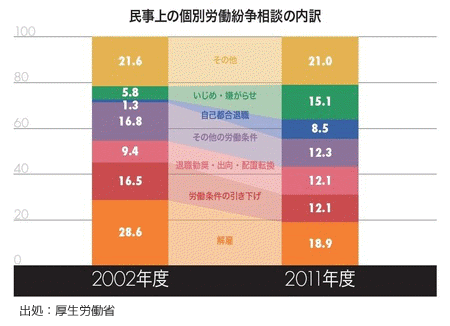
これら統計データから分かるように、企業にとって労務問題(労働問題)は常に身近に生じ得る問題です。
また、いったん労務問題(労働問題)が現出し個別労使紛争(個別労働紛争)と化すと、一挙に経営の「緊急重要課題」になりうる性質を有しています。
しかし、経営者は一般的に経営課題のなかで人事労務の分野は優先順位を低く置く傾向があり、経営の重要課題との認識は極めて弱いものがあります。
特に中小企業では、経営者側の危機管理意識の不足や情報不足、時間不足があります。
人事労務の問題は、日々の事業運営の中で頻繁に経験できるものではないため、経営者は経験値が不足しています。
そのためか、従業員にこんなことをしたり言ったりします。
まさに自分の言動で個別労使紛争(個別労働紛争)の火種をばらまいているようなものです。
日本の労働法制では、労働者は手厚く保護されていることも適切に認識しておかなければなりません。
紛争がこじれて裁判になってしまうと、多くの場合は立証責任を企業側に求められます。
「サービス残業が常識だよ」といくら声高に言っても、手帳にメモした勤務記録を証拠に「2年間で2000時間分の残業代を払え」と労働者が主張したら、それを反証する証拠を会社は用意しなければいけません。
労務問題(労働問題)を防ぐには、就業規則(就労規定)や各種規程、職場のルールブック、そして経験豊富な人事労務の専門家(人事労務を得意とする社会保険労務士、弁護士)を積極的に活用し、労使が共通の認識を持ち、認識のズレを解消する必要があります。
日頃からこのような取り組みをしていても、個別労使紛争(個別労働紛争)は起きてしまいます。
起きてしまったら、次は「初動」が極めて重要となります。
初動を誤り、後々大きな損失を被らないよう、初動段階で紛争解決に長けた人事労務のプロ(紛争解決を得意とする社会保険労務士、弁護士)を積極的に活用することが、結果的に解決の近道となります。
労働条件の明示は、書面を交付する事項と口頭で差し支えない事項と、2種類あります。平成11年の法改正以前は賃金に関する事項だけが書面による通知事項でしたが、現在では次の5事項が規定されています。...
1件中:1 - 1